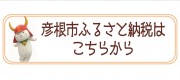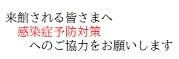兜は、甲冑の中で頭部を守る防具です。その構造は、頭を覆う鉢(はち)と首の後ろを守る(しころ)から成っており、それぞれ戦闘形態の変化とともに、さまざまな形に変化していきました。
兜は、甲冑の中で頭部を守る防具です。その構造は、頭を覆う鉢(はち)と首の後ろを守る(しころ)から成っており、それぞれ戦闘形態の変化とともに、さまざまな形に変化していきました。
日本における兜の使用は古墳時代に遡り、その形式は中国大陸や朝鮮半島の影響を受けたものでした。平安時代になると、日本独自の甲冑様式が整い、細長い鉄板を縦に接ぎ、継ぎ目を鋲(びょう)で留めた星兜(ほしかぶと)が誕生します。この形式は、室町時代まで標準的な兜の形となり、江戸時代になっても制作されました。星兜に次いで南北朝時代に登場したのが筋兜(すじかぶと)です。鉢の構造は星兜と同様ですが、鋲を平滑に仕上げることで、シンプルな造形となり、星兜に比べ軽量である点が特徴です。
星兜や筋兜が多数の鉄板を用いるのに対し、数枚の鉄板で形成するのが頭形兜(ずなりかぶと)です。頭形兜は、室町時代から制作され始め、甲冑の需要が高まった戦国の世においては、数多く流通しました。その背景には、鉄板の加工技術の向上によって、少ない鉄板を効率的に組み合わせることが可能となり、大量に生産できるようになったことが挙げられます。
戦国時代には、頭形兜のようにほぼ同一の形式で量産された兜がある一方、人々が入り乱れる戦場で、自身の存在を主張するため、あるいは敵を威嚇するための奇抜なデザインを用いた変わり兜も作られました。変わり兜の多くは、西洋の兜を模した形、動物や植物、器物などを象った形で表されます。これらの意匠を設ける際、多くの場合が、粗い鉄板を数枚組み合わせた簡素な鉢の上に、和紙などで成形した意匠を据える張懸(はりかけ)という技法が使用されており、変わり兜が、防具としての強度より、装飾性に重きを置いたことを物語っています。
本展では、館蔵の兜の中から、さまざまな形の作品を展示します。それぞれの機能や意匠はもちろん、その形が制作されるに至った背景などを紹介していきます。兜が持つ防具としての機能だけではなく、造形の美しさにもご注目ください。