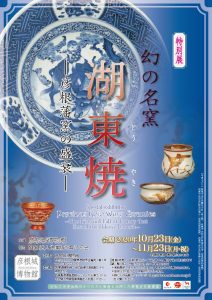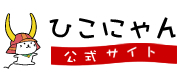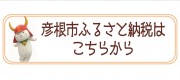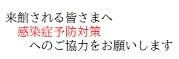このたび、彦根城博物館では、5年間かけて調査を進めてきた井伊家伝来古文書(近代文書)18,306点の調査が完了し、その成果を収録した報告書を作成しました。
当館では、平成28年度から令和2年度までの5年間、文化庁の補助金の交付を受けて、井伊家伝来古文書(近代文書)の調査を実施してきました。これは、旧彦根藩主である井伊家に伝わった古文書のうち、近代(主に明治から昭和戦前期まで)のものを対象に、史料目録を作成することで、古文書の適切な保管と活用につなげることを目的としたものです。井伊家で働いていた家職の業務日誌や、彦根城の管理、井伊直弼の顕彰活動、井伊家も経営に関わった彦根製糸場などに関する史料があり、近代の井伊家や彦根の歴史を知ることができます。
報告書は、主に県内外の図書館に寄贈しました。彦根市立図書館等でご覧いただけます。彦根城博物館学習コーナーにも配架しますが、同コーナーは現在コロナ対策のため利用できません。
※なお、販売は行っておりません。近隣の図書館でご利用ください。
名 称:「井伊家伝来古文書(近代文書)調査報告書」
【紙 版】
判 型:A4判
ページ数:第1巻 368ページ
第2巻 448ページ
第3巻 448ページ
【CD-R 版】
紙版の報告書全頁のPDFデータと目録部分のExcelデータを保存
内 容
○調査概要・近代の井伊家概要・解題 (24頁)
調査概要、近代の井伊家やその家政組織などについての簡単な解説、解題
(目録に収録している古文書について、分類ごとにどのようなものがあるか
簡単に解説するもの)。
○史料目録 (1,218頁)
井伊家近代文書18,306点を、主に内容面から分類して、古文書1点ごとに
名称、作成者、宛名、年月日、形状などの情報を一覧にした目録。
詳しくは、こちらをご覧ください。